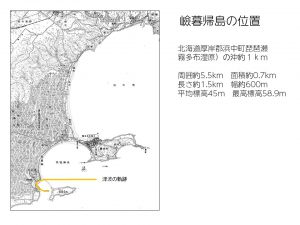浜中町は、60年前のチリ沖地震で津波を被っています。霧多布湿原の中央に(海岸から1.5km程)朽ちた船があるのは、この津波で海から流されて来たからだと聞いています。すなわち、60年前には津波を被って一度リセットされましたが、それからの40年間で、海岸までトウキョウトガリネズミの生息域が拡大したことになります。以前の堤防は低く、人間も簡単に登り降りできるものでしたので、本種も霧多布湿原との往来は比較的簡単にできたのかもしれません。本来、高潮で波を被る可能性のある場所であることから、その生息地は何回も壊滅的な打撃を受けていたと推察されます。しかし、そこに本種の個体群が維持されていたということは、霧多布湿原から本種が何度も海岸まで移動して来たと考えるのが自然です。新しい堤防はかなり高く反っているため、本種が堤防を越えて海岸まで再び進出するのかは判りませんが、霧多布湿原に本種の個体群が存続し続ければ、再び海岸でも本種の生息地が形成される可能性があることになります。
浜中町は、60年前のチリ沖地震で津波を被っています。霧多布湿原の中央に(海岸から1.5km程)朽ちた船があるのは、この津波で海から流されて来たからだと聞いています。すなわち、60年前には津波を被って一度リセットされましたが、それからの40年間で、海岸までトウキョウトガリネズミの生息域が拡大したことになります。以前の堤防は低く、人間も簡単に登り降りできるものでしたので、本種も霧多布湿原との往来は比較的簡単にできたのかもしれません。本来、高潮で波を被る可能性のある場所であることから、その生息地は何回も壊滅的な打撃を受けていたと推察されます。しかし、そこに本種の個体群が維持されていたということは、霧多布湿原から本種が何度も海岸まで移動して来たと考えるのが自然です。新しい堤防はかなり高く反っているため、本種が堤防を越えて海岸まで再び進出するのかは判りませんが、霧多布湿原に本種の個体群が存続し続ければ、再び海岸でも本種の生息地が形成される可能性があることになります。
以上のことから、私が教訓としているのは、「目先の生息地の保全だけを考えていたら、2つの重要なもの失う。」ということです。 それは、「住民の信頼と協力」 と「その希少種にとって、一番重要な生息地」ということです。
希少種を守るためには、住民の協力無しにはできません。さらに、状況によっては、住民にとって、不自由さや経済的影響を受け入れてもらわざるを得ないことも生じます。しかし、それを受け入れてもらえるのも信頼関係が成立したからこそです。したがって、保全を主張する側は、地域の状況をできるだけ考慮した上で、保全方法を提案する責任があると考えます。

トウキョウトガリネズミの研究をしていますと、「生息地の保護が必要ですよね。保護運動はしないのですか。」という趣旨の質問を度々されます。しかし、私はこれまで生息地の保護ということを前面に出して活動はしてきませんでした。それは、「希少種=守る必要がある=見つけた生息地を守れ」という、短絡的な思考では本当には守れないと考えているからです。それは、この教訓によるものです。
私は普段から環境アセスメントや地域づくりになどに関わっていますが、現状はかなりかけ離れています。その話については、別の機会にしたいと思います。
自然災害で命を失うのは、人間も野生生物も同じです。人間の命を守ることが、野生生物の命も守ることにも繋がるということも視野に入れて、環境保全は検討されることも重要だと考えます。私は、この一面も大切したいと思って活動しています。
改めて、東日本大震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈り致します。